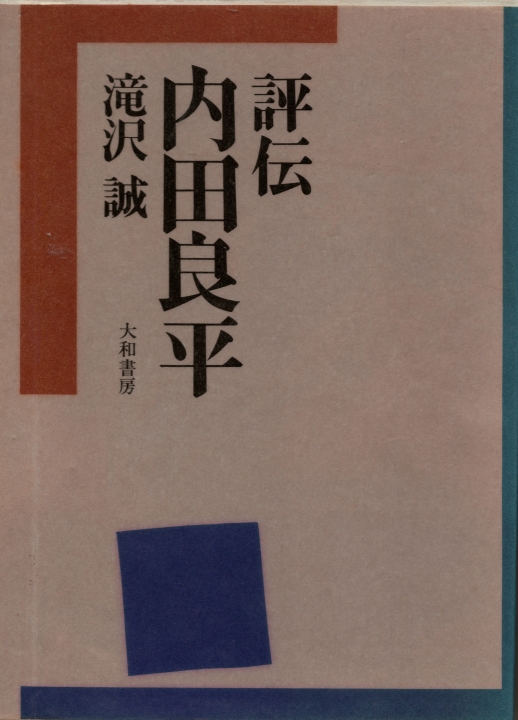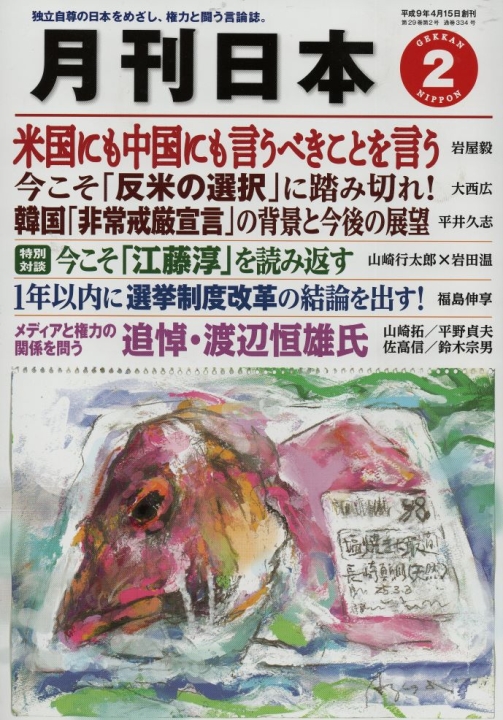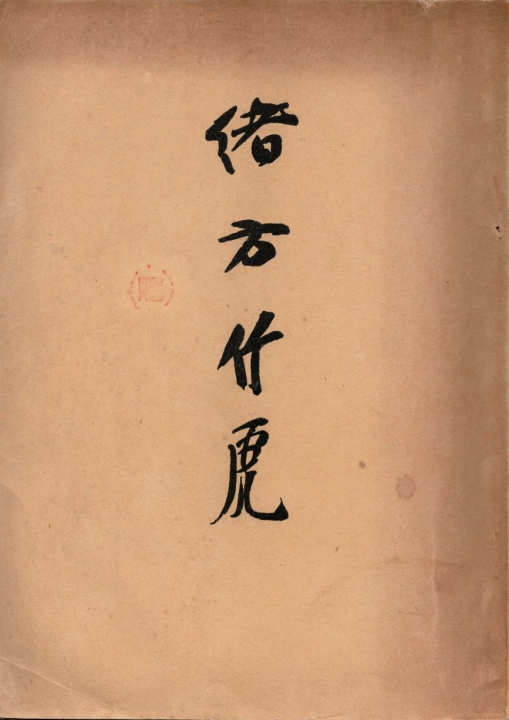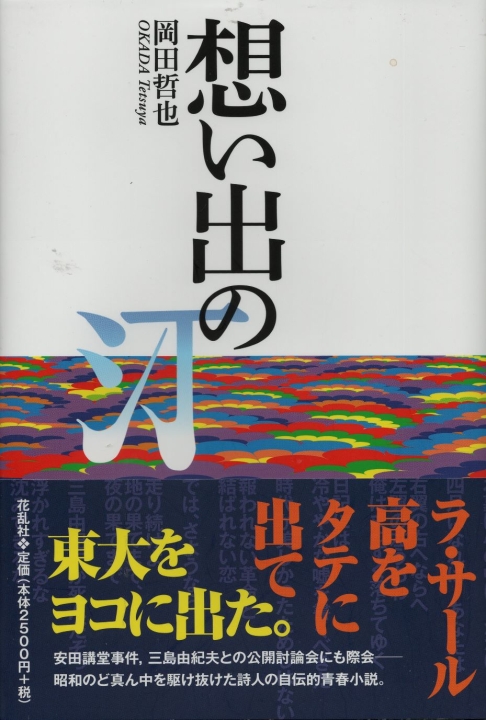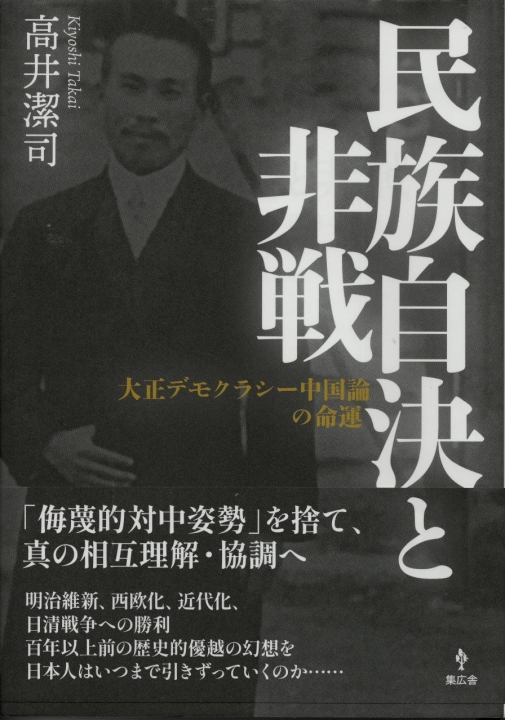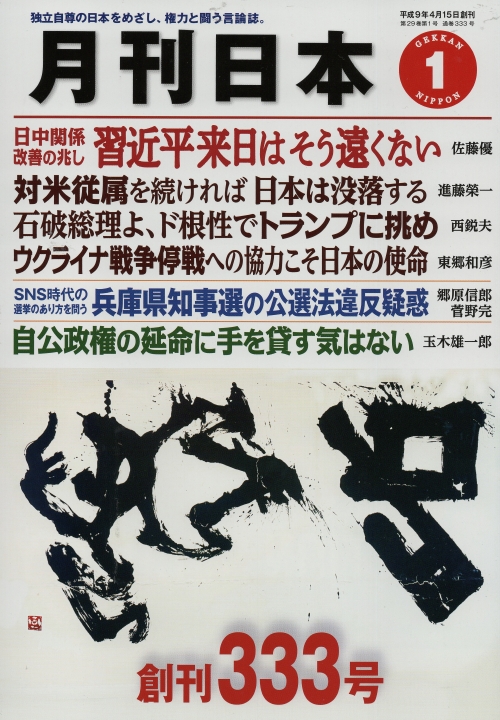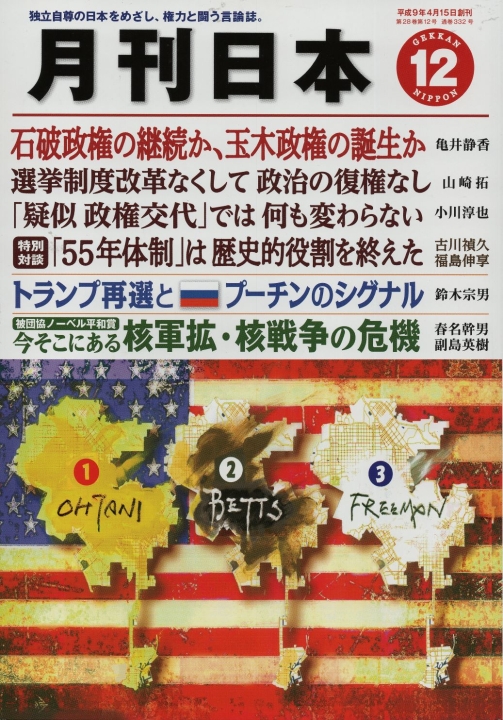目 次のコピー
99.『評伝 内田良平』滝沢誠著、大和書房、1976年
98.『民族自決と非戦』高井潔司著 集広舎(月刊日本2月号掲載)
97.『緒方竹虎』修猷通信・大塚覚発行、私家版、昭和31年
96.『想い出の汀』岡田哲也著、花乱社、2024
95.『民族自決と非戦』高井潔司著 集広舎
94.『戦後レジームからの脱却を』久保田勇夫著 産経新聞出版「月刊日本1月号」掲載93.『在野と独学の近代』志村真幸著 中公新書「月刊日本12月号」掲載
92.『日本の禍機』朝河寛一著、由良君美校訂・解説、講談社学術文庫2021年
91.『落日燃ゆ』城山三郎著、新潮文庫
90.『それでも日本人は「戦争」を選んだ』加藤陽子著、新潮文庫
89.『南北朝異聞 碧鏡』河合保弘著、つむぎ書房
88.『アメリカ革命』上村剛著 中公新書「月刊日本10月号」掲載
87.『矢吹晋著作選集』矢吹晋著 未知谷 「月刊日本」9月号掲載
86.『マハン海上権力論集』麻田貞雄編・訳、講談社学術文庫、2010年
85.『大鳥圭介の英・米産業視察日記』福本龍著、国書刊行会、2007年
84.『シギント 最強のインテリジェンス』江崎道朗、茂田忠良著 ワニブックス 「月刊日本」8月号掲載
83.『「米欧回覧」百二十年の旅』泉三郎著、国書出版社、1993年
82.『軍都久留米』山口淳著 花乱社 「月刊日本」7月号掲載
81.『枝吉神陽』大園隆二郎著、佐賀県立佐賀城本丸歴史館
80.『黒船前夜』渡辺京二著 弦書房 「月刊日本」6月号掲載
79.『工作・諜報の国際政治』黒井文太郎著、ワニブックス
78.『命の嘆願書』井手裕彦著、集広舎「月刊日本」5月号掲載
77.『武田範之とその時代』滝沢誠著、三嶺書房
76.『権藤成卿 その人と思想』滝沢誠著、ぺりかん社、1996年(再版)75.『安東省菴』松野一郎著、西日本新聞社
74.『優しい日本人が気づかない残酷な世界の本音』川口マーン恵美・福井義高著 ワニブックス
73.『命の嘆願書』井手裕彦著、集広舎
72.『出口王仁三郎 帝国の時代のカリスマ』ナンシー・K・ストーカー著、原書房
71.『造船記』野田雅也著、集広舎
70.『中国人権英雄画伝』宇宙大観著、集広舎
69.『日本人最後のファンタジスタ』河合保弘・笹川能孝著、つむぎ書房
68.『風船ことはじめ』松尾龍之介著、弦書房
67.『言志四録』佐藤けんいち編訳、ディスカヴァー・トゥエンティワン
66.『渋沢栄一(上・下)』鹿島茂著、文春文庫
65.『頭山満・未完の昭和史』石瀧豊美 花乱社 「月刊日本」1月号掲載
64.『ガネフォ60周年記念誌』ガネフォ会・水球チーム編
63.『江戸という幻景』渡辺京二著、弦書房
62.『GANEFO その周辺』宮澤正幸著、拓殖大学創立百年史編纂室
61.『カイザリンSAKURA』河合保弘著、つむぎ書房
60.『欧州統合の政治史』児玉昌己著、芦書房
59.『藍のおもかげ』澁谷繁樹遺稿集、澁谷繁樹著、岡田哲也編、花乱社
58.『今日も世界は迷走中』内藤陽介著、ワニブックス
57.月刊日本9月号掲載 『ドキュメンタリーの現在』 臼井賢一郎、吉崎健、神戸金史 石風社
56.『デュオする名言、響き合うメッセージ』立元幸治著、福村出版
55.『現代ユーラシアの地政学 EU・中国関係とハンガリー』児玉昌己著、久留米大学法学部
54.『45年余の欧州政治研究を振り返って』児玉昌己著、久留米大学法学部
53.『儒学者 亀井南冥・ここが偉かった』早舩正夫著、花乱社
52.『ハマのドン』松原文枝著、集英社新書
51.『詩集 サラフィータ』前野りりえ 著、書肆侃侃房
㊿『うどん屋おやじの冒険』語り・青木宣人、聞き手・宮原勝彦、集広舎
㊾『中国はなぜ軍拡を続けるのか』阿南友亮著、新潮新書
㊽『幕末の奇跡』松尾龍之介著、弦書房
㊼『踏み絵とガリバー』松尾龍之介著、弦書房
㊻『老子・列子』訳者・奥平卓、大村益夫、経営思潮研究会
㊺『絹と十字架』松尾龍之介著、弦書房
㊹『CIAスパイ養成官』山田敏弘著、新潮社
㊸『世界を動かした日本の銀』磯田道史、近藤誠一、伊藤謙ほか著、祥伝社新書
㊷『天誅組の変』舟久保藍著、中公新書
㊶『長崎蘭学の巨人』松尾龍之介著、弦書房
㊵『新・「NO」と言える日本』金文学著、高木書房
㊴『日本の軍事的欠点を敢えて示そう』江崎道朗 かや書房(月刊日本6月号掲載)
㊳『ステルス・ドラゴンの正体』宮崎正弘著、ワニブックス
㊲『なぜこれを知らないと日本の未来が見抜けないか』江崎道朗著、KADOKAWA
㊱『亀井昭陽と亀井塾』河村敬一著、花乱社
㉟『作戦術思考』小川清史著、ワニブックス
㉞『オンライン脳』川島隆太著、アスコム
㉝『スマホ脳』アンデシュ・ハンセン著、久山葉子訳、新潮新書
㉜『第三次世界大戦はもう始まっている』エマニュアル・トッド著、文春新書
㉛『陸・海・空 究極のブリーフィング』小川清史、伊藤俊幸、小野田治、桜林美佐、倉山満、江崎道朗 共著
㉙『ウイグル人という罪』清水ともみ、福島香織著、扶桑社
㉘『光陰の刃』西村健著、講談社文庫
㉗『負け戦でござる。』小野剛史著、花乱社
㉖『「明治十年丁丑公論」「痩我慢の説」』福澤諭吉著、講談社学術文庫
㉕『福翁自伝』福澤諭吉著、岩波文庫
㉔『連帯綾取り』三浦隆之著、海鳥社
㉓『管子』松本一男訳、経営思潮研究会
㉒『遥かなる宇佐海軍航空隊』今戸公徳著、元就出版
㉑『宇佐海軍航空隊始末記』今戸公徳著、光人社
⑳『維新の残り火・近代の原風景』山城滋著、弦書房
⑲『いのちの循環「森里海」の現場から』田中克監修、地球環境自然学講座編、花乱社
⑱『ちいさきものの近代 Ⅰ』渡辺京二著、弦書房
⑰『天皇制と日本史』矢吹晋著、集広舎
⑯『インテリジェンスで読む日中戦争』山内千恵子 ワニブックス(「月刊日本11月号掲載)
⑮『大衆明治史 (上)建設期の明治』菊池寛著、ダイレクト出版
⑭『木村武雄の日中国交正常化 王道アジア主義者石原莞爾の魂』坪内隆彦著、望楠書房
⑬『振武館物語』白土悟、集広舎
⑪『大アジア』松岡正剛著、KADOKAWA
⑩『人は鹿より賢いのか』立元幸治 福村出版
⑨『人口から読む日本の歴史』鬼頭宏著、講談社学術文庫
⑧『データが示す福岡市の不都合な真実』 木下敏之著、梓書院
⑦『インテリジェンスで読む日中戦争』山内智恵子著、江崎道朗監修、ワニブックス
⑥『孫子・呉子・尉繚子・六韜・三略』訳者村山孚、経営思潮研究会
⑤『シルクロード』安部龍太郎著、潮出版社
④『日本人が知らない近現代史の虚妄』江崎道朗著、SB新書
③『漢民族に支配された中国の本質』三浦小太郎著、ハート出版
②『台湾を目覚めさせた男』木村健一郎著、梓書院
①『緒方竹虎と日本のインテリジェンス』江崎道朗著、PHP新書