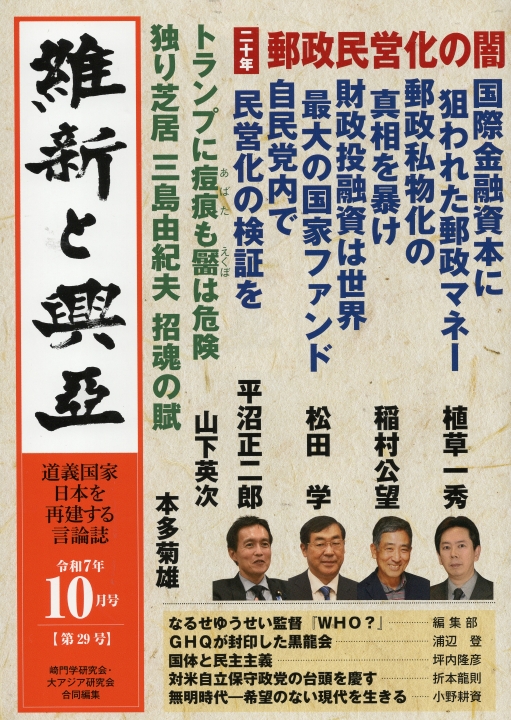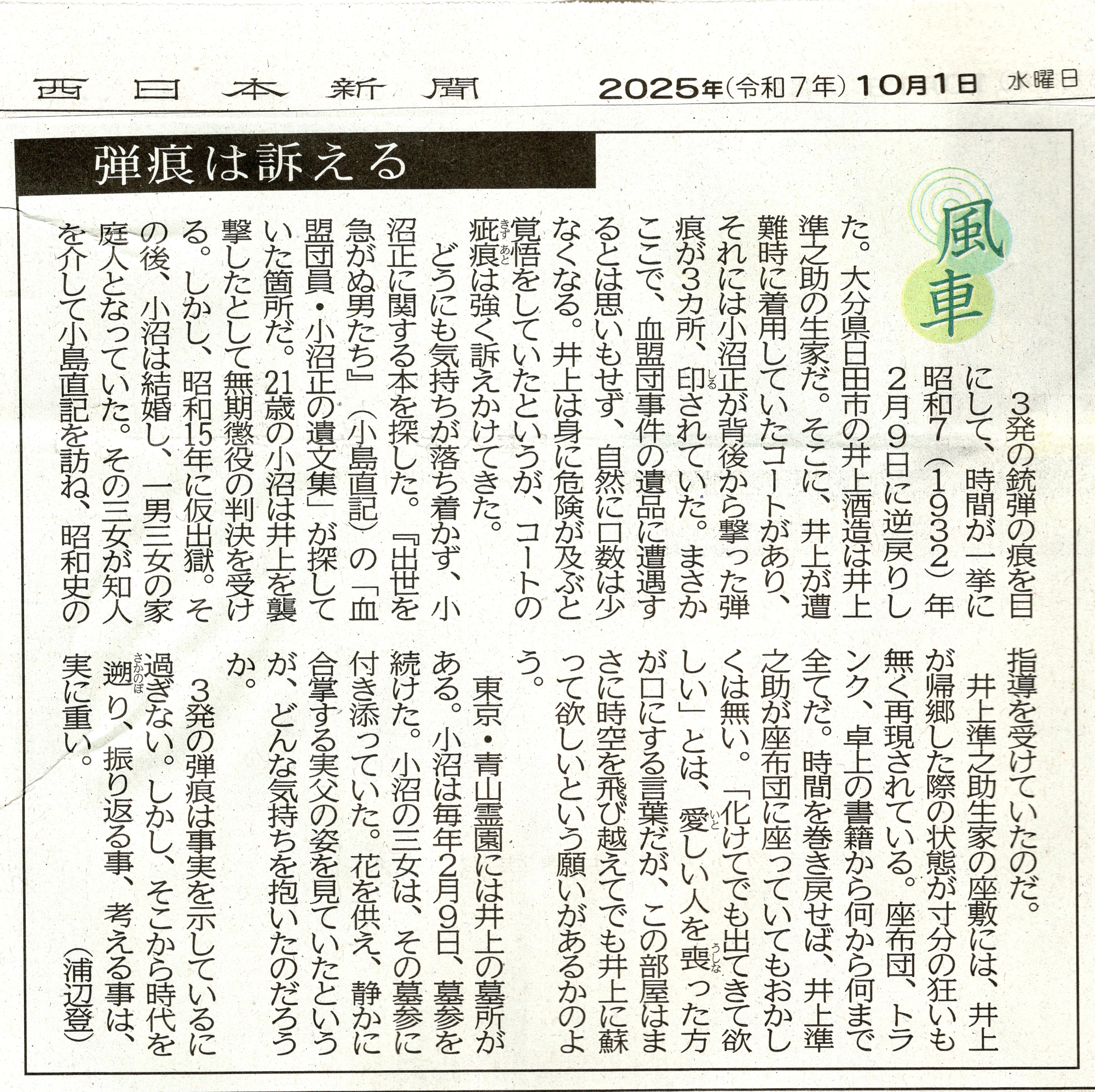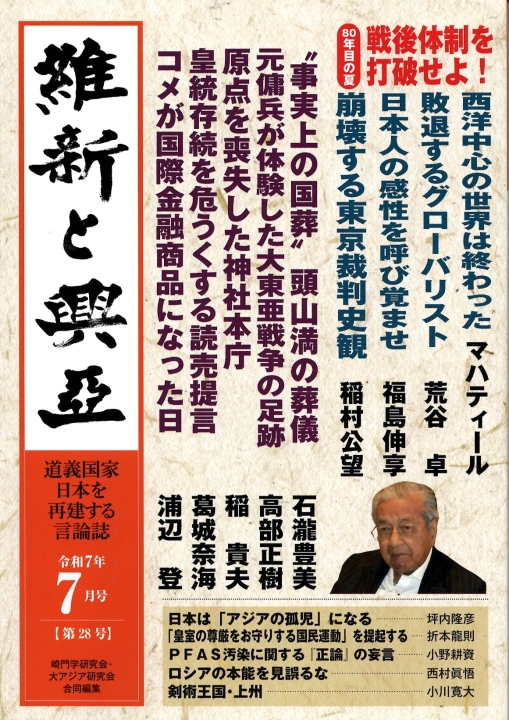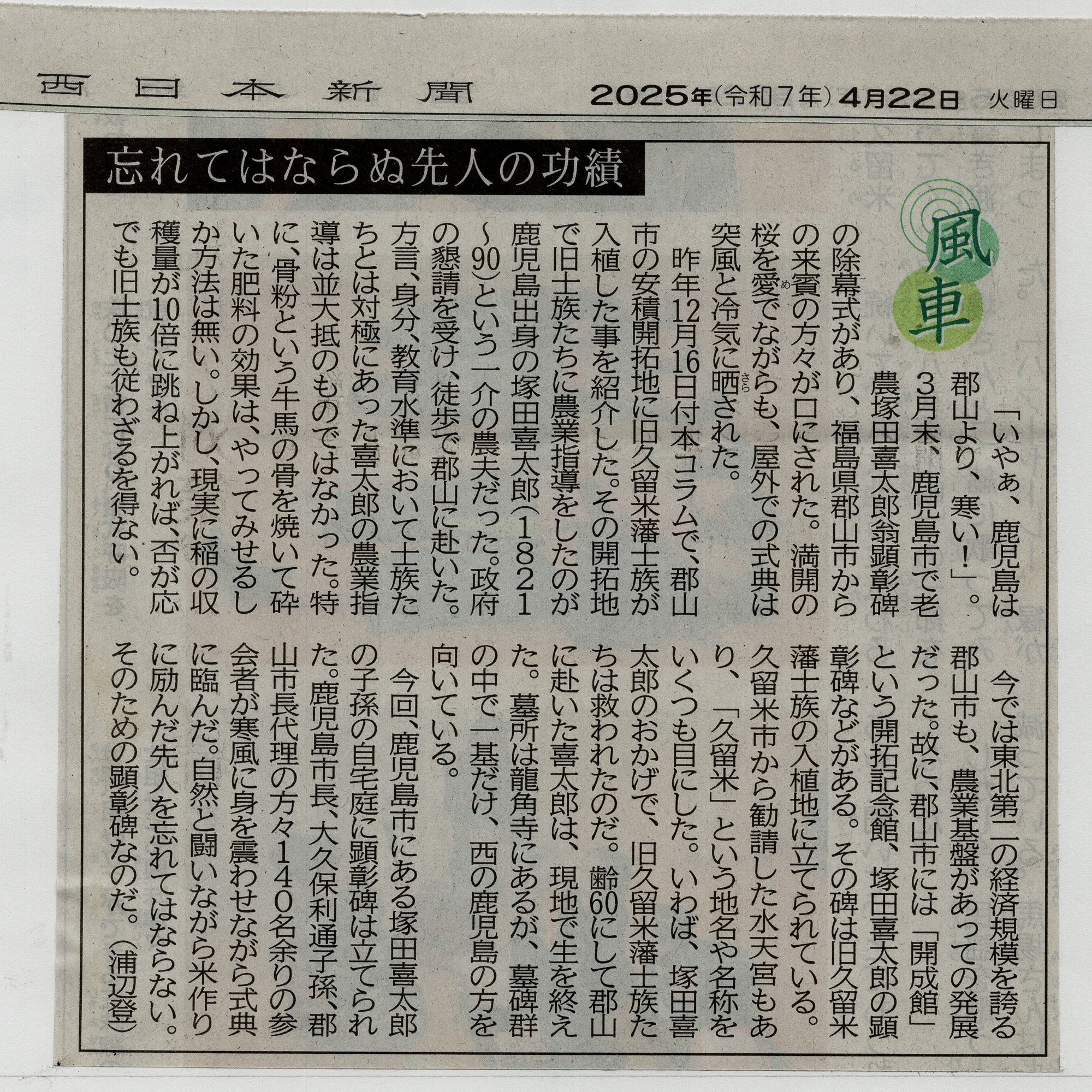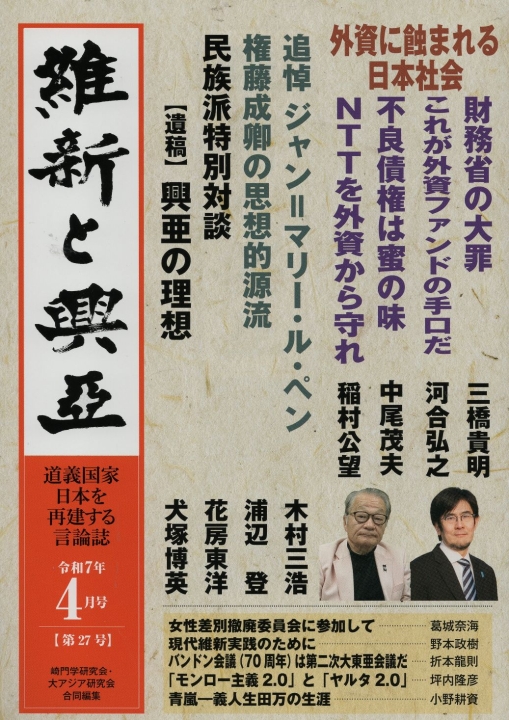五・一五事件の思想の背景をたどる
前号(令和6年3月号)において、五・一五事件での海軍青年将校らが集った香椎温泉旅館跡に立つ「曙のつどい」碑を紹介した。その碑の裏面には、血盟団事件、五・一五事件、二・二六事件が一連の行動であると刻まれている。現今、これらの事件は個別に扱われ、とりわけ、二・二六事件は陸軍の皇道派と統制派の対立として教える。
そもそも、なぜ、五・一五事件(昭和7年、1932)の海軍青年将校らは蹶起したのだろうか。大正10年(1921)のワシントン軍縮会議での統帥権干渉問題。農民の困窮を顧みない癒着した政財界の糾弾。アジアの植民地解放という動機が考えられる。しかし、その動機、思想の背景に人的関係、風土の気質が関係していたのではないか。そう考えるのも、海軍青年将校たちの出身地が佐賀県に集中しているからだ。佐賀県の思想といえば山本常朝の『葉隠』、水戸学の系譜に連なる枝吉神陽(1822~1862)の「義祭同盟」が有名だ。今も、佐賀市の龍造寺八幡宮に隣接して楠正成父子を祭神とする楠神社があり、拝殿脇には義祭同盟碑もある。海軍青年将校らの思想に何か風土的な影響があるのでは・・・と思い、佐賀県を訪ねた。
佐賀市を訪ねる
令和6年(2024)1月、佐賀県佐賀市に向かった。通常、佐賀市に行くには福岡市中心部からは博多駅を経由する。しかし、筆者が居住する福岡市西部からは唐津駅(佐賀県唐津市)経由でも行くことが可能。そこで今回、唐津駅を経由し、JR唐津線で佐賀駅に至るコースを選択した。このコース上には、海軍青年将校の村山格之、黒岩勇の故郷である佐賀県多久市、小城市を通過する。地の気というか風土を見てみたいということもある。
唐津駅からは昔懐かしい2両編成のディーゼルカーに揺られる。この沿線には昔、三菱鉱業相知(おおち)炭鉱があり、石炭を満載した列車が往来した場所であり、唐津市はその昔、石炭の積み出し港として栄えた町だった。車窓からの田園風景を楽しむ。
唐津線の多久駅、小城駅を経ておよそ1時間、高架線となった佐賀駅に到着。ここから佐賀鍋島家の居城であった佐賀城跡にある佐賀県立図書館まで歩いてみる。一直線の大通り左右には平成30年(2018)に開催された「佐賀維新博覧会」で主役を務めた鍋島直正、大隈重信、江藤新平らの銅像が林立している。それらを一つ一つ写真撮影しながら図書館に至る道を歩く。途中、旧長崎街道に面しての龍造寺八幡宮、楠神社にも立ち寄り参拝。あの「義祭同盟碑」も確認する。
五・一五事件は海軍青年将校が主導し、陸軍青年将校、民間人が関係した事件だ。この海軍青年将校の中心人物は藤井斉(1904~1932)だが、藤井は第一次上海事変で戦死し、直接に事件には関係していない。しかし、この藤井の意思を継ぎ、三上卓、黒岩勇、村山格之、古賀清志らが蹶起し、犬養毅首相や警視庁などを襲撃した。この藤井、三上、黒岩、村山、古賀(長崎県佐世保生まれの佐賀育ち)らは佐賀県出身であり、ここに、何か郷土特有の思想、風土があるのではないかと考えた。佐賀県立図書館の郷土資料コーナーで、海軍青年将校らの出身地である佐賀県多久市、小城市に関連する資料を探ってみる。
藤井斉に関する資料
まず、藤井斉の資料を探してみる。佐賀県立図書館架蔵の小城郷土史研究会会報誌で藤井斉についての記録を目にした。その中に、意外にも血盟団事件での領袖である井上日召(1886~1967)についても含まれていた。井上は満洲の公主嶺(吉林省)にあった仏心寺で参禅したが、仏心寺は佐賀県小城市芦刈町の福田寺(曹洞宗)が本寺と記されている。福田寺の二十世住職は東大心(あづまだいしん)であり、二十一世として福田寺を継承する予定であった東祖心(あづまそしん)が檀家の娘と恋に落ち、満洲に逃避して開いたのが仏心寺である。そして、満洲に道を求めて流れきた井上日召が訪れ参禅したのが仏心寺である。日召が満洲の地で座禅を組んでいた背景には、禅寺(福田寺)が根本にあったことに少なからず驚いた。
従前、日召が茨城県大洗町の護国堂(日蓮宗)にいて、そこに海軍霞ヶ浦航空隊(茨城県土浦市)に所属する藤井斉らが集ったと思っていた。しかし、藤井は旧制佐賀中学(佐賀県立佐賀西高校)に通学する途次、福田寺の近くを通学路にしていた。末寺の満洲・仏心寺にやってきた日召との関係性は見えない糸で早くにつながっていたのだった。実際に、藤井が日召に合ったのは野口静雄(佐賀県出身)の伝手だった。野口は拓殖大学から安岡正篤の金鶏学院に学び、茨城県職員となっていた。この金鶏学院に野口がいたことから藤井は権藤成卿ともつながった。
藤井斉は旧制佐賀中学を経て海軍兵学校に入校。将来を嘱望される海軍士官となったが、政治改革についての考え、意見を有していた。この思想の背景には満洲・仏心寺の本寺である福田寺が影響していると見るべきではないか。清水芳太郎が編集した『五・一五事件』によれば、維新遂行のため藤井が古賀清志、村山格之、三上卓、伊東亀城、大庭春雄に団結を呼びかけた。その後、伊東が山岸宏に、古賀清志が中村義雄に、三上卓が林正義、黒岩勇を勧誘。林が塚野道雄を引き込んだ。同郷の海軍青年将校らが集結し、志を同じくする仲間が行動するのも時間の問題でしかなかったということになる。
蛇足ながら、1963年のインドネシアで開催されたガネフォ(令和6年1月号参照)に紀地三明の変名で日本側関係者として加わっていた黒岩勇の妻は福田寺の檀家の娘という。
九州は「水戸学」の故地なのか
五・一五事件に関係した海軍青年将校の故郷を訪ねることで、「何か」を得ることができるのではないかと思っていたが、意外な事に気づいた。それは「水戸学」の故地は九州ではないのかということ。
そもそも、「水戸学」は水戸光圀の「大日本史」編纂事業が基礎となり、明国の儒学者である朱舜水(しゅしゅんすい、1600~1682)が日本に亡命したことが起爆剤となる。この舜水だが、明国が清国(満洲族政権)に侵略されたことで万治3年(1660)に長崎にやってきた。当初、その舜水の生活を支えたのは筑後柳川藩(福岡県)の儒学者安東省庵(あんどうせいあん、1622~1701)であり、朱舜水の長崎滞在の申請書を長崎奉行に提出し、佐賀小城藩主の鍋島直能が同意をしたことで安堵を得たのだった。朱舜水のおよそ6年にわたる長崎滞在生活は安東省庵、鍋島直能の支援によるものだった。安東省庵は自身の禄の半分を師である舜水に捧げた。
やがて、水戸光圀(1628~1701)とは書簡を交わすほど親しい関係にあった小城藩主の鍋島直能の推挙もあって舜水は水戸光圀の招聘に応じた。朱舜水といえば、後醍醐天皇(1288~1339)の忠臣楠正成(1294~1336)を見出し、「楠公賛」などの漢詩を著した。これが楠公精神として幕末の勤皇の志士たちの精神的支柱となるが、安東省庵は長崎在住中の朱舜水に楠正成について詳細な紹介文を送り、舜水の意見を求めていた。一般に「水戸学」といわれるが、その故地は九州にあったのではないか。
ちなみに、安東省庵が朱舜水を知るきっかけとなったのは、弟子の権藤宕山(ごんどうとうざん)がもたらした。宕山とは、あの権藤成卿の五世前の先祖になる。この縁も不思議といえば、不思議だ。